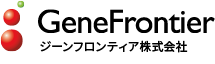鋳型DNAについて
-
Q1:鋳型DNAの作製と最適化のポイントを教えてください
鋳型DNAの作製と最適化のポイントにつきましては、以下のページにまとめてありますので、ご覧ください。
鋳型DNAについて
鋳型DNAの配列に関する6つの注意点 -
Q2:目的タンパク質の遺伝子の上流に必要な配列を教えてください。
鋳型DNAには、目的タンパク質をコードする遺伝子の上流に、T7プロモーター配列とリボソーム結合部位(SD配列)が最低限必要です。
-
Q3:T7プロモーター以外のプロモーターは使用できますか?
PUREfrex®の反応液には、転写酵素としてT7 RNAポリメラーゼが含まれていますので、T7プロモーターを付加した鋳型DNAの使用を推奨しています。他のプロモーターを使用する場合は、そのプロモーターに対応したRNAポリメラーゼを添加して反応してください。
-
Q4:5’UTRの配列を変えることはできますか?
はい。
ただし、5’UTR配列がタンパク質合成量に影響することがわかっています。5’UTR配列が合成収量に与える影響を調べたポスターを参照ください。今のところ、弊社が設計した5’UTR配列 (T7Pro-SD primer)が最も高いタンパク質の合成量を示しています。配列中の各領域によって、合成量に及ぼす影響が異なりますので、実験に目的に応じて調整してください。[T7Pro-SD primerの塩基配列]
5′-gaaattaatacgactcactatagggagaccacaacggtttccctctagaaataattttgtttaactttaagaaggagatatacca-3′ -
Q5:終止コドンはどれが使用できますか?
PUREfrex®に含まれる2種類の翻訳終結因子(解離因子)は、3種類存在する終止コドン(UAA(オーカー)、UAG(アンバー)、UGA(オパール))の全てに対応しているため、いずれの終止コドンも使用できます。
-
Q6:目的タンパク質の遺伝子の下流に必要な配列を教えてください。
環状DNAを使用する場合は、目的タンパク質をコードする遺伝子の下流に、転写を終結させるT7ターミネーター配列が必要です。直鎖DNAを使用する場合、終止コドンの下流に10塩基以上の塩基を付加してください。直鎖DNAの場合は、終止コドンの下流にT7ターミネーター配列は必ずしも必要ではありません。
-
Q7:2段階PCRによりPUREfrex用の鋳型DNAを調製する場合、”REV primer”の「10塩基以上の任意の配列」に制約はありますか?
“REV primer”について、基本的には任意ですが、いくつかポイントがあります。
・ORF部分のC末端以降の”taatga”となる部分は終止コドンを2つ並べた配列になっています。
・配列よりも、長さの方が重要で、10塩基より短いと合成効率に影響が出てきますが、10塩基よりも長い分には、20塩基等でも大丈夫です。
・できるだけ、終止コドン直後に固い二次構造を形成するような配列(GC含量が高いなど)は避けてください。
・例えば、この部分に制限酵素サイトを入れることができます。 -
Q8:反応液にどのくらいの鋳型DNAを添加すればよいですか?
プラスミドやPCR産物に関わらず、DNAは、1kbpあたり0.5-3 ng/µLになるように添加してください。
PUREfrex反応液に添加するDNAは、分子数(モル濃度)が基準となっており、最終濃度が 2nM 前後となるように添加してください。例えば、反応液に添加するDNAがプラスミド(環状DNA)で、その長さが6kbpの場合、実際のORFの長さに関係なく、(0.5~3)x6=3~18ng/μLとなります。 -
Q9:鋳型DNAをTEバッファーに溶解して使用することはできますか?
TEバッファーに含まれるEDTAは、転写・翻訳反応を阻害してタンパク質合成量を下げることがあります。DNAを溶解する際には、EDTAを含まないバッファーやミリQ水などを使用することをおすすめします。
-
Q10:PCR反応液を直接添加する際の注意点はありますか?
PCR反応液からの塩などの持ち込みを抑えるため、添加量はPUREfrex®の反応液量の1/10 以下にしてください。転写・翻訳反応とも、PCR反応液からの持ち込みによる塩濃度の変化などによって活性が低下します。
PCR産物量が不足している場合は、未精製のPCR反応液の添加量を増やすことは避け、DNA精製キットなどを用いて十分な濃度になるようにDNA溶液を調製してください。
【参考】PCR産物を鋳型DNAとして使用する場合 -
Q11:PCR産物はどのくらいの純度が必要ですか?
PCR後の電気泳動で目的産物以外にバンドが見られる場合は、PCR条件を検討して副産物の生成を抑えてください。副産物からもタンパク質が合成されることがあり、PCRで得られるバンドの純度がタンパク質の合成効率に影響します。PCR条件を変更しても副産物が生じる場合は、目的のバンドをゲルから切り出して精製してください。ゲルから切り出す際には、DNAの損傷(転写反応が阻害されます)を防ぐために紫外線は照射しないでください。ブルーライトは使用可能ですが、できるだけ照射時間を短くしてください。
【参考】 PCR産物を鋳型DNAとして使用する場合 -
Q12:人工合成DNAを鋳型として使用することはできますか?
プロモータ配列込みで人工合成したフラグメントを、鋳型DNAとして使用することは可能です。また、ORFのみを合成したDNAから、プロモーター配列など必要な配列を含むプライマーを使用してPCRで鋳型DNAを作成して使用することもできます。しかし、遺伝子合成のメーカーによっては、納品物にタンパク質の合成反応を阻害するRNaseが含まれていることがあります。目的タンパク質が合成できない場合は、RNaseインヒビターの添加やRNaseの不活化をお試しください。
また、プラスミドの形態で納品されるのものについては、プラスミドを鋳型DNAとして用いる場合の注意点もご確認ください。 -
Q13:鋳型DNAとして使用できるプラスミドベクターはどんなものがありますか?
T7 promoter、SD配列、T7 terminatorを含むベクターが使用できます。例えば、pET系(Merck社)、pQE系(Qiagen社) 等があります。但し、lac operator配列が存在すると、タンパク質合成量が減少する場合がありますので、lac operator配列を含まないベクター(pET17など)をおすすめします。
-
Q14:鋳型のプラスミド調製の注意点は何ですか?
プラスミドDNAを調製する際は、精製時に使用したバッファーに添加したRNaseの活性が最終精製物に残っていないことが重要です。
例えば、Qiagen社のQIAprep Spin Miniprep Kitや、Promega社のWizard Plus SV Minipreps DNA Purification Systemのようなメンブレンタイプの精製キットを使用した場合、Lysis bufferに含まれるRNase Aが最終精製DNA溶液にも混入しています。このまま鋳型DNAとしてPUREfrex®の反応液に添加すると、転写産物などのRNAが分解されタンパク質の合成が阻害されます。
このタイプの精製キットで精製したDNA溶液の場合、Phenol/Chloroform処理によりRNaseを失活させた後、エタノール沈殿などにより再度精製することで、RNase活性を含まないDNA溶液を調製できます。あるいは、RNase inhibitorをPUREfrex®の反応液に添加することで、タンパク質を合成できるようになります。一方、Qiagen社のPlasmid Mini Kitでは、樹脂に結合したDNAを溶出後、溶出液にisopropanolを加えてDNAを沈殿させるため、RNase活性の混入が抑制されます。このキットで精製したプラスミドを、そのまま使用できることを確認しています。
【参考】プラスミドを鋳型DNAとして用いる場合の注意点 -
Q15:RNAを鋳型として使用するにはどうすればよいですか?
mRNAからタンパク質を合成する場合、開始コドンの上流にSD配列を含むmRNAを使用してください。また、mRNAの添加濃度の目安は0.1~1 µMです。ご使用のmRNAの配列や純度等により最適濃度は異なりますので、はじめに、上記の濃度を参考に最適な添加濃度を決める条件検討をおすすめします。